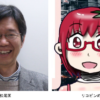Look East
マレーシアのマハティール首相(93)は7日「第15回日本の次世代リーダー養成塾」の講義のために訪れた福岡県宗像市で、戦争放棄を明記した日本国憲法について「戦争に加担しないという模範にすべき平和憲法。マレーシアの憲法にもこの条項を加えたい」と述べた。https://t.co/Ou7RbjQqxn
— Jin Teng Zhang Yang @ 懇請支持 (@kakiaki1005) August 8, 2018
マレーシアの辣腕の政治家、マハティールは言った。「Look East」。
もっとアジアを、私たちの身のまわりの国々を語ろう。フィリピンはかつてスペインンの植民地(その国名はフェリペ2世に由来する)、米西戦争後はアメリカの植民地であり、太平洋戦争中の日本の3年間の占領を経て内実ともに独立を果たす。そのため東南アジア唯一のキリスト教国であり、英語とフィリピノ語(タガログ語)が公用語である。
フィリピンには独特の小売市場がある。それが、津々浦々にみられるサリサリ・ストアである。その歴史は古く、中華圏やイスラム圏との貿易で栄えていた12世紀には存在したという説もある。
サリサリとは、雑多な、くさぐさの、といった意味であり、要は雑貨を販売する零細小売店である。その総数は2010年にフィリピン全体で77万軒と推定されている。ざっくり計算してフィリピン国民の100人にひとりがサリサリ・ストアを経営しており、マニラ首都圏では10世帯にひとつがサリサリ・ストアという調査もある。当を得ているか分からないが、日本の自動販売機に比すものがある。
その販売形態はサシェ・マーケティング(Sachet Marketing)と呼ばれるもので、まとめ買いしたものを小袋(Sachet)ごとにばら売りする。少しだけ上乗せして売るので、商品ひとつ当たりの値段じたいは高くなる。これが店のもうけになる。フィリピンではこの販売形態が非常に一般的であり、たとえばフィリピンの10人中7人はタバコを箱ではなく1本ごとに買うと言われている。
サリサリ・ストアには露天商も多いが、典型的なそれは自宅がそのまま店舗となる。店主は近くの大手量販店で商品を買い込み、それをばら売りする。ここで疑問がおこる。なぜ多くの人は量販店を利用せず、割高なサリサリ・ストアを好むのか。そしてなぜ、サリサリ・ストアどうしでは競争が起きないのか。賢明なホモ・エコノミクスならば、同じ商品をできるだけ安く買おうとし、またできるだけもうけを増やそうとするのだから、サリサリ・ストアは買い手にも売り手にもメリットがないのではないか?

Homo Oikonomics
それはBOP(ベースオブピラミッド)つまり低所得者層ビジネスだからだ、というのが教科書的な説明だ。量販店でまとめ買いしそれを保管するだけの余裕がなく、遠出せずにその日にその場で必要な物だけを「少なく、何度もless, more often」買う低所得者向けに発達したというわけである。だがこの説明にも限界がある。フィリピンより貧しい国や地域は東南アジアにかぎってもたくさんある。しかし、そこではかならずサリサリ・ストアのような零細小売業が発達している、というわけではない。また、フィリピンの近年の経済発展を経てもサリサリ・ストアは存続している。
ところで――経済(Economy)はギリシア語のオイコス・ノモスに、また、~ノミクスという派生もノミコスというギリシア語に由来する。オイコスは家あるいは共同体、ノミコスは管理運営のことである。という薀蓄はどうでもいいけど、サリサリ・ストアを個人の利潤の最大化として捉えるかぎり、あるいは利潤を額面だけで評価しようとするかぎり、その存在意義は見えてこない。実際には、サリサリ・ストアにはフィリピンの社会に根差した価値がある。
第一に、サリサリ・ストアを訪れる客のほとんどは店主と顔見知りである。売り手と買い手は同じ地域の出身者であり、同じ階層に属し似通った経済状況にある。ただ、店主の方がその場所に長く住み、知己も多く、生活は安定している傾向にある。そして第二に、サリサリ・ストアで交換されるのは商品だけではない。情報も一緒に交換される。多くの客は店主や他の客と雑談する。それは職探しや役所の手続きや争いの仲裁といった切実な話題を含み、生活上の具体的な問題と解決に直結していることが多い。購入する商品も生活用品のほかにタバコやお菓子のような嗜好品が多く、ときにはほとんど場所代と言った方がいい。何も買わずに出て行くのは気兼ねするから、というわけである。
というわけで、サリサリ・ストアはフィリピン低所得者層の相互扶助文化である、と考えるのが正しいだろう。それは人間関係を密接に保ち、問題を共有し、孤立しないためのネットワークを作り出すものとして機能しているのである。これらは一朝一夕に形成されたものではない。サリサリ・ストアの維持のためには、すでにサリサリ・ストアのネットワークが緻密に張り巡らされていることが必要なのであり、だからこそフィリピンの外でどこでも見られるわけではないし、経済発展の波にも動じずに続いているのである。
Gender Role
フィリピンの人びとにとって、サリサリ・ストアは「すでにそこにあったもの」である。その保守性を裏付けるのがジェンダーである。そこそこ安定した生活基盤があれば自宅で開業できるサリサリ・ストアは、その多くが女性店主で占められている(露天商型のサリサリ・ストアの売り手は男性が多い)。要するに、家事育児と兼業できる仕事なのだ。そしてだれもがサリサリ・ストアとともに育ったのである。
こうした店主は、フィリピンの政治単位であるバランガイ――その名は植民地以前の古代社会に由来し、開発独裁を進めたマルコス政権時代に「復活」した――で発言権を持っていることも多い。例えば、再開発に反対する住民組織の担い手がこうしたサリサリ・ストアの店主である。
低所得者層の経済的自立という点でもサリサリ・ストアは重要であり、マイクロファイナンスの主要な融資先である。例えばCARDはフィリピンで最初にマイクロファイナンスを始めた組織であり、主に農村の貧農女性層の経済的自立化を図っている。2013年に、CARD Inc.からマイクロファイナンスを受けている人数は62万5千人に上り、その返済率は99.4%を達成している。その融資総額の10~15%はサリサリ・ストアの女性向けであったと推定されている。
CARDに限らず、グラミン銀行をはじめとするマイクロファイナンスの対象者は9割以上が女性である。これは、貧困ライン以下の世帯の男性が収入をギャンブルや飲酒・喫煙などに消費してしまう傾向があるのに対し、女性の場合は経済的自立のみならず子供への養育や教育に使用する傾向があり、返済率も高いからである。
まとめよう。サリサリ・ストアとは、フィリピンに根付いたシェアリングエコノミーである。それは台所の食糧棚(パントリー)のシェアであり、情報のシェアであり、生活空間のシェアである。
Reference
Rodolfo P. Ang & Joseph A.Sy-Changco 2007 “The phenomenon of sachet marketing: Lessons to be learned from the Philippines” Enhancing Knowledge Development in Marketing vol.18
サシェ・マーケティングを貧困ビジネスではなく、一般的なマーケティング戦略としてとらえる。
舟橋豊子2012「BOP市場における流通と消費の実態 ―フィリピンのサリサリ・ストアを事例にして―」経営学研究論集 第37号
都市と農村両方のサリサリ・ストアの実態調査。
太田麻希子2009「重層する戦略の場としての住民組織」アジア研究 vol.55 No.3
住民組織におけるサリサリ・ストア女性店主のプレゼンスについて。
林悼史ほか2013「BOP層の経済的自立化と自律的ビジネス生態系 ―フィリピンCARDのマイクロファイナンスとサリサリストアの事例分析を中心として―」経営論叢 第3巻第1号

京大卒の一般企業のサラリーマン。趣味は植物観察。