2018年、シェアリングエコノミーは著しく発展した。

2008年創業のAirbnb、翌年にUber、5年後に日本でメルカリが生まれた。約10年間でシェアリングエコノミー企業は、どんな経済学者の予想よりも爆発的に成長した。
スマホやタブレットなどのデジタルモバイル技術の発展に伴い、オンデマンドサービスやオンデマンド商品への利用レベルは加速し、シェアリングエコノミーの根幹である『所有を越えたアクセス』までもうすぐというところまで行きついた。
2019年のシェアリングエコノミー予想
World Economic Forum 4 big trends for the sharing economy in 2019では、次の10年間前後のシェアリングエコノミーをいくつか予測できると述べられている。
2019年、プラットフォームを社会に浸透させていくことの次の段階になる。それは株式公開である。
今年度、Uber、Lyftの両方が新規株式公開(IPO)を目指す動きが始まった。Uberは1200億ドル(947億ドル)、Lyftは150億ドル(118億ドル)の価値がついた。
Whether drivers will share in any upside remains to be seen.
シェアリングエコノミーの市場規模で日本の約100倍を示している国家・中国では、意外にもユニコーン系企業が苦戦している。
バイクシェアリングのユニコーン「ofo」は、株主による預金の払い戻しが押し寄せて破産の危機に瀕していると報告されている。
ー4 big trends for the sharing economy in 2019から引用ー
2009年と比較して大幅に市場規模を拡大したものの、株主関係で一気に危機的状況に陥った「ofo」のようにUberなども運営に失敗した場合、
もはやシェアリングエコノミーは順調と言えないだろう。
シェアリングエコノミーの参入事業拡大
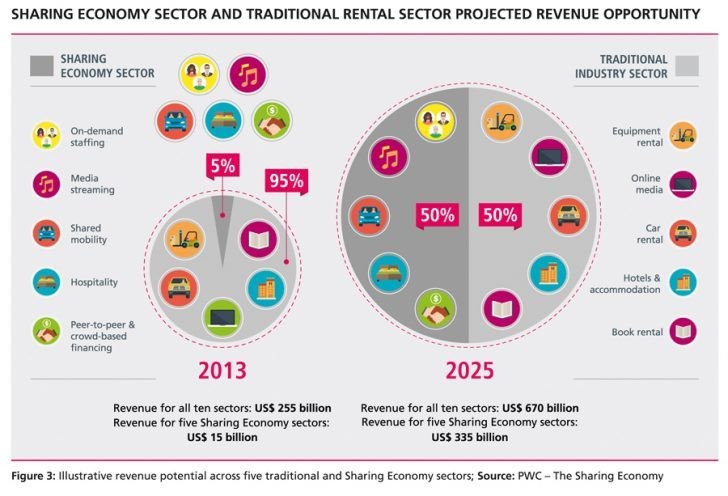
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/sharing-economy/
シェアリングエコノミー企業は、様々な事業への参入している。Uber(Uber Eats含み)、Airbnb、だけでも相当大規模になるが、
モバイルデータ通信のシェアを推進するMOOVERの登場、長野県では町おこしの一環として空き家をワークシェアオフィスとして利用する事業など、さらなるシェアリングエコノミーの拡大が行われている。
https://twitter.com/naganoNTK/status/1087897303665393665
都市で行われる規制
2018年に導入された京都市民泊条例など、シェアリングエコノミー企業と行政の対立は、日本でも例外なく起きている。
しかし、先ほど紹介した地域の活性化を担うシェアリングエコノミー企業など、現在は対立と協働の狭間と言えるだろう。
例えば、アムステルダム市は高齢者や低所得者向けにシェアサービスの割引券を発行している。

誰もが容易に利用できるプラットフォームは、地域の為に活かされる未来も少しずつではあるが見えてきている。
利用者の多様化へ
シー・エコノミー(SHE-economy)は、女性の起業、生活、働き方などの女性に関する経済圏を総称する言葉である。
現在、複数の英語サイトが誕生し事業を展開する見込みである。
これからダイバーシティーが進む中で、運用者が永遠に若者であることも、男性であることも絶対的とは言い切れなくなっていくだろう。
シェアリングエコノミーはどこまで変えていくのか?
千葉銀行上海駐在員事務所 拡大する中国のシェアリングエコノミー 中国レポート2017年8月号
geppo 編集部です。
テクノロジー、シェア、政治に関する幅広いジャンルのニュースをお届けします。ご意見・ご感想は、お問い合わせフォームまで!









